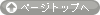授業の中で、学習者の言語パフォーマンスを詳細に「見取り」、長期的な展望に立った様々な「関わり」を持つことが教師に求められています。
本事業の位置づけ
本事業は、平成24年度科学研究費補助金(基盤研究C 一般) 「小・中学生の「言語力」を育成・評価する方法の実証的・実践的研究」において進められている教師と学習者間のコミュニケーション研究を基盤にしている。特に、学習者の言語パフォーマンスを定点的に捉えるのではなく、教師や他の学習者とのコミュニケーションを通して、学習者個人の言語パフォーマンスが質的に向上することを学習行為として捉え、その多様な学習の方向性を教師の「見取り」から始まる教育的コミュニケーションを対象にしている。
「インターベンション」の意義
「教科を超えた言語活動の充実」が小中学校を中心に進められてすでに4年目に入る。学習者の主体性と協働性の高い学習が、各教科の学習に内面的な思考と認識を言語化する機会を増加させ、概念や方法的知識が教室という空間で顕在化しやすくなり、従来の講義型の授業よりも量的にも質的にも学習効果を高めている。
授業の構成が、学習者の「主体的学習活動」や「協働的学習活動」で占められるようになると、当然教師の役割も変化してくる。松友(2008)では、こうした教師の役割を「ファシリテーター」「コーチ」「インタープリター」として捉え直し、学習者に任せきりになるのではなく、活動に誘い、活動の質を高める支援を行い、活動を位置づける教師の主体的な教授行為を計画的に遂行していく必要性を指摘した。
しかし、日々に授業の中では、こうした「言語活動」と「学習者」を結びつける行為だけではなく、学習者の「言語力」を育成するために、長期的な展望と即時的な見取りに基づいて対話的に遂行する「インターベンション」が不可欠である。松友・大和(2012)では、こうした長期的な展望に立ち、学習者個々人の「言語力」育成を目的とした教師の対話的教授行為を言語・非言語両側面から抽出し、その類型化と効果について検討を加えた。また牧田(2012)においては、学習者の思考の深化を促す「装置」としての教師のインターベンションを客観的に分析している。
両研究が、教師の主体的視座からのものであるか、分析者としての客観的なものであるかは別にして、教師と学習者個人の関係性を対象にして分析をしている点は共通している。教師が自らの学力観や学習観を生かして学習者の言語力を育成するために、計画的に学習者個人と対話する行為は、「教授=学習」過程に「個の学び」を成立させ、学習者個人の主体的学習活動を生み出す働きを持っている。
これに対して、一柳(2009)で扱われている教師の「リボイジング」のような教授行為は、即時的な状況判断に基づく行為であり、具体的には、学習者相互をつないだり、学習課題に対して並列的に出された学習者の発言を分類、整理するような「言語活動」に協働性を持たせ、維持する働きを持っている。
「言語活動」の授業への導入は、学習者が他の学習者に自分の考えを説明したり、学習者相互に自分の意見を交流させたり、班での話し合いなどで自分たちの意見を吟味したりする学習にかなりの時間を割くことにつながる。言うまでもなくこれらの学習場面は即時性の高いコミュニケーション場面であり、教師の効果的なインターベンションに支えられなければ、学習者は言いたいこと言っているだけで、コミュニケーションが成立しない。これらの活動が「学習活動」として授業の中で機能するために、教師にはその場で学習者の表現内容や学級の状況などを「見取り」、より多くの学習者の参加を促しながら思考の深化を生み出すような「コミュニケーション場面」を作り出していく必要がある。
こうした、多角的で複雑な教授行為を授業のまさに「その場」で行わなければならないようになってきた点で、「言語活動」を取り入れた授業を行うことは難しいのである。こうした教授行為そのものの変容に対応するためには、学習者の表現内容の質を捉える「眼」の形成、学習者の発言から思考や認識、表現の方法をメタ認知して抽出し言語化する「眼」の形成に加え、学習者相互をつなげたり、学習課題を焦点化して話し合いを深化したりするコミュニケーション技術の習得が求められている。
インターベンションの類型
学習に協働性を生み出すための教師の「インターベンション」
授業における教師のコミュニケーション技術の研究は、「教育話法」や「指導的評価言」など個人の学習効果を高める目的で行われるものに焦点化される傾向が強く、そこで扱われるコミュニケーションも「教師対学習者個人」の一対一の対話とそれを傍観する他の学習者の関係性の中で分析されてきた。これは、学級集団における学習活動を捉える視点が「集団学習」と「個の学習」という二元論に陥っており、「教授=学習過程」はその往復運動に支えられているという認識に拠るものである。
しかしこの捉え方は、「集団学習」に内在する「個の学習」を見落とす結果となり、「個の学習」の不断の連続性を「集団学習」という仕切りによって分断して捉えてしまうことにつながっている。さらにこれは、学習そのものを教師の視点もしくは教師の計画性の上で把握することを意味しており、「学習者の視点」から捉えた「学習活動」を見えなくしてしまう。
例えば教師がいくら班学習を組織しようとも、学級全体で話し合いを組織しようとも、学習者個人がこうした用意された学習に参加する能力がなかったり、参加することに対してネガティブな意識を持っていたりする場合、連続する「個の学び」は存在していても、「集団学習」との往復運動は生じていないことになる。これが、授業でいくら集団学習を組織しても、実際にうまくいかない大きな原因である。教師は、学習過程の組織に加え、学習者個々人の「教室」への参加状況や能力を「見取り」ながら、その場で「協働性のある学習場面」を作り出していかなければならない。
こうした協働性の高い「場」を教室の中に作り出していく教師の教授行為は、例えば教室掲示の整備や学級文庫など学習内容に関する情報を供給するなど環境的側面での働きかけに加え、協働的な学習に対して学習者のポジティブな意識を形成するための長期的なカリキュラムを構成したり、協働性の高い場面に参加するための言語力を育成したりする意識や能力を育成する働きかけも含まれる。
しかしこれらの教授行為は、協同性のある学習場面を教室に作り出すための間接的な働きかけなのであり、最も直接的な働きかけである「教師のインターベンション」が効果的に行われなければ、こうした学習場面を教室に作り出すことはできない。