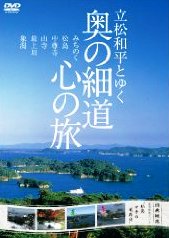教材について
音読させたい。奥の細道は本当にリズムがいい。こんなリズムのいい文章はなかなかない。漢文調の文章だとか、漢語の多用だとか、その理由はいくつもあるのかも知れないが、サクサクサクと小気味良いテンポで音読することができれば学習者もこの作品とうまく出会えたような気がする。そればかりを目標にして、難読語や古語の学習をさせるのもいいかも知れない。
旧仮名遣いを現代仮名遣いに直すことは、もう三年生だから完成期だと思うのだけれど、内容を理解しつつ音読すると一層効果が出るように思うので、その点を目標に据えたい。そういう意味では、初段と平泉はホントに読み甲斐のある箇所だと思う。
芭蕉の認識
平泉に限って言えば、芭蕉はなぜ涙したのか、という点を起点に課題解決型の学習をよく実践してきた。 芭蕉が目にしている実際の景色と、彼が自分の歴史的な知識によって再現している頭の中の景色とが相対化されるが故に、時代の流れが人為を超越してしまうことに目を向けていることが分かる。 また、無常観には一足飛びには絶対行かない。「変わるもの」と「変わらないもの」の二項対立だけでは芭蕉の認識にはたどり着けないと考えているからだ。
藤原氏三代の栄耀も、義経の功績もみんな時代の流れの中で一瞬の出来事のように消え去ってしまう、それに対して雄大な自然は時間の流れに対してしっかりと存在し続けている。確かにそれはそうだけれど、それだけでは、人為のむなしさから出家でもしたくなってしまう。芭蕉は、人間の知識や記憶の中に生き続ける人為を確かに受けついていく、語り継いでいくこと、をいうのではないか。故に彼は旅をするし、個人の足跡を追い、人為を再認識するのではないか。
月日は
初段というと暗記させたいという思いが先ず来る。「月日は百代の過客にして・・・」という部分を暗唱させることで、なにやら教養が付いたような気になる。リズムは確かにいいし、何度も口ずさんでみると自己満足の世界に浸れる。ああ古典を学んでいるのだなあと実感を持つ唯一の瞬間かもしれないし。 「おくのほそ道」を読むといつもその生活感のなさに不思議な感じを覚える。行く先々で、土地土地の名家を句会に誘い込む。曽良の大切な仕事だ。江戸から有名な先生がやってくる、十分にもてなしておかないと・・などといって土地土地の名家は金をつぎ込む。また贅沢旅行がしたいなあ、うまいものも食いたいし・・・等と思っている芭蕉のにやけ顔が目に浮かぶようだ。
文化人だから質素倹約を表向きに据えておかないとまずいし、世捨て人的な俳風も損なわれてしまう・・・。弟子からの寄付も途絶えてしまうと非常に困る。芭蕉をスパイだという人もいれば、忍者だという人もいる。真摯に彼の叙述に向き合ったときに感じる一種のうさんくささや、関所の厳しい当時にあれだけ自由に各地をめぐることができたことの不思議さも、出自が未詳なまま伊賀の出身だとかいうことも言われたりするから余計に考え込んでしまう。
江戸初期の社会事情を鑑みれば、どうしても清貧の俳人としてはとらえられない彼の文章には、貧しさを感じることはできない。そうしたことをすべて含み込みながらも、これだけの名文を書かせるだけの教養と歴史的認識力に圧倒される現代人はなんと脆弱なのだろうかとも思う。
古典作品に向き合う教師は、もうすでにそこにひれ伏している。逆らいがたい名作への敗北感を漂わせながら、絶対視される作品を教え込んできた。だから、芭蕉自身と教師も向き合わないしもちろん学習者も向き合わない。でも日本人はこういう人が大好きだ。自分にはできない自由な暮らしをする人が大好きだと思う。当時の人がこの初段を読んでどう思ったのだろうかなどということを考えさせたい。半分以上の人は理解できず、ある一部の酔狂な人が素晴らしいと絶賛したのかも知れないし、芭蕉の弟子たちの聖典として大切に扱われてきたのかも知れない。
すみかもないし財もない、風の吹くまま漂泊する芭蕉の生き方を中学生にどう向き合わせたらよいのだろうか?こういう人生もいいねではすまない、芭蕉の旅への熱い思いを受け止めさせることが本当にできるのか、多分無理だと思う。生活自体があまりにかけ離れすぎているのだから、中学生自身が自分たちと芭蕉とを結びつける接点のようなものがない。時代の隔たりをいいわけにして何となく感じさせて済ませるわけには行かない。
船頭も馬方も、旅人ではない。家庭もあれば家族もいる、一生活者だ。かなり教材の権威性を崩してみたのだけれども、授業を考えることにはなりません・・・。
平泉
平泉は、まじめに取り組もうと思いながら、芭蕉の認識について考えてみました。芭蕉が見ているのは江戸時代の平泉ですから、「大門」「秀衡の館」も跡でしかなく田野になっていますし、高館に登ってみても実際には山と川が見えるだけです。 しかしながら、芭蕉は非常に感動して俳句を詠み、涙を落とすのです。これはいったいなぜなんだろうかという点を起点にして課題解決型の学習を仕組んでみるのも一つの手かと思います。
芭蕉の心の中に映る景色は、藤原三代の栄耀の時代の景色なのか、それとも両方を長い時間の中でとらえているのか、いずれにせよ、500年以上経た当時、残っているのは自然のみで人為の跡など全くないと言った状況なのでしょうから、芭蕉を涙させたものがいったい何であったのかを探っていくことが、この章段のポイントになるのは間違いないと思います。
ようは探り方をどうするかという問題なのであって、絵を描かせるなり、して実際に見えている景色と芭蕉の心の中の景色と二つの景色を相対化させるところまではつれていかなければならないように思います。 ちょっと一工夫すると、現代の人為に満ちて自然の少なくなった平泉の風景も合わせて三者で考えさせるとまた違った感じを学習者が抱くと思います。学習者も当事者にした上で、時間の流れとはいったい何か?ということを考えさせるのも面白いかなあと。
芭蕉にとっての歴史的知識
後半部分は前半とは異なり、過去の遺物を保管している場所に行っています。本来ならば、雨風雪などでぼろぼろになっていても良いところを、「四面新たに囲みて」と人の手によって過去の遺物が保管されている事を対象にし、「しばらく千歳のかたみとはなれり」といっています。 非常に微妙な言い方ですが、ここに注目しておかないと「五月雨や降り残してや光堂」の句意がつかめないから非常に重要なポイントといえます。
つまり、降り残すとはいったい何を指しているのかが読めないのです。また、そうやって自然の風化から免れた遺物の存在に触れて詠む句ですから、光堂の存在が芭蕉にどのように映ったのかということが理解できます。このように理解すると、芭蕉の無常観も微妙な部分があることが分かります。人為は自然の流れの中で消え去っていくものだと考えているのかどうか疑わしくなります。長明などは、だから何にも残さなくていいんだと考えそうですが、芭蕉はそこまでストイックにものを考えられなかったのではないでしょうか。失われた景色を自分の歴史的知識によって再生し、過去の遺物を保管する現地の者の心に触れ、それでもなお時間の流れの中での人為のはかなさに嘆き悲しみ諦観を抱いたのかどうか?このあたりを学習者と一緒に考えてみたいものだと思います。