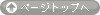協同の知を探る
植田一博・岡田猛 編著 共立出版 2000
目次
第一部 認知科学の問題としての協同
第二部 研究事例
第一章 協同行為と相互作用
第二章 共有される認知空間と相互作用による創発の出現可能性
第三章 協同による科学学習における問題を中心に据えた探索
第四章 親子の協同による科学学習の実際とその支援
第五章 ダイナミックな意思決定におけるグループによる問題解決
第六章 認知科学ー その学際性について
第七章 金融市場における意図せざる協調現象
概要
本書を購入したきっかけは、九州大学大学院教授の丸野氏の研究に触れたことであった。国語科教育におけるコミュニケーション能力育成の共同研究グループの一員として研究を進めはじめてはや5年目になるが、丸野氏のこれまでの研究が以下に優れたものであるかは一目瞭然だった。氏の研究成果を追っていくうちに本書に至ったというのが正直なところだ。
それはさておき、いうまでもなく認知科学は人間の行為の奥底にある意識の構造や流れを明らかにしようとする考え方をベースにしている。様々な行為や現象における人間の意識の有り様を明らかにしてきた研究の流れの中で、「協同行為」における意識の有り様を明らかにしようとしたのが本書である。
今まで、個人の頭の中を見ようとしてきた認知科学が、複数の人間が協同して何かを行う際の意識の有り様をみようというのであるから、おのずと興味がわいた。人間相互の意識の相関関係をどうやって捉えるのだろうかとか、社会学的な相互関係論をどのような位置に置いて研究をするのだろうかとか、いろいろと興味深い疑問がわいた。
人間関係はフラットである場合よりも、バイアスのかかる場合の方が多い。つまり、個人の意識の有り様と協同作業における意識の有り様はダブルバインドの状態にあり、そのどちらを選択するかは、人間関係のバイアスに影響を受けるとは言えても、ダイレクトに影響を受けるわけではない。ここが一番の難所だろうなあと思う。協同作業はつねに関係の放棄という危険性を孕みながら、(特に学習では)進められるものだ。折り合いをつけたり譲歩したりする心の働き方が起こりうるのは学校ではなく「お仕事」の場合だけだし、その場合異常にストレスがかかることになることも事実だ。
それでもなお、一人でやるよりも、複数でやるほうが効果的であるということを証明するのはとっても難しいことだ。でもそこを譲ってしまうと、単に現象を分析するだけの研究に落ちてしまう。
本書は、日本の頭脳が、この難問に挑んだ結果が記されている。